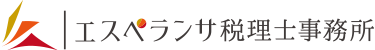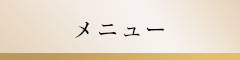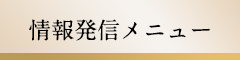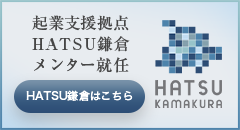給与からの税金や社会保険料の控除が、どのように手取り額に影響しているかご存知でしょうか?
今回は、給与所得者が活用できる一般的な節税対策について詳しく解説します。
ドクターと税金【5】給与所得者の一般的な節税対策|金融セミナー
目次
- 節税効果が高いiDeCoとNISA
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- NISA(少額投資非課税制度)
- 節税と楽しみを両立する「ふるさと納税」
- 医療費控除で思わぬ出費を節税に
- 住宅ローン控除の活用(条件付き)
- まとめ
節税効果が高いiDeCoとNISA
給与所得者にとって、効率よく税金を抑えるための代表的な制度がiDeCoとNISAです。
iDeCoは、個人で運用する年金制度で、積み立て金額が全額所得控除の対象となります。
メリット:所得税と住民税の負担を軽減。年間で最大7万円以上の節税効果が期待できます(税率50%の場合)。
注意点 ::投資商品の運用益にリスクが伴うため、長期的な視点が必要です。
メリット:所得税と住民税の負担を軽減。年間で最大7万円以上の節税効果が期待できます(税率50%の場合)。
注意点 ::投資商品の運用益にリスクが伴うため、長期的な視点が必要です。
新しいNISAでは、1800万円の非課税枠が設定されています。この枠内で運用することで、売却益や配当金に通常課される20%の税金が非課税となります。
メリット: 長期運用において圧倒的な節税効果。
注意点 :非課税枠を有効活用するため、計画的な投資を心がけることが重要です。
メリット: 長期運用において圧倒的な節税効果。
注意点 :非課税枠を有効活用するため、計画的な投資を心がけることが重要です。
節税と楽しみを両立する「ふるさと納税」
ふるさと納税は住民税の使い道を変更する制度ですが、節税効果だけでなく、返礼品を楽しむこともできます。
仕組み
お住まいの自治体に支払う住民税の一部を、他の自治体に寄付として振り分けます。結果的に、寄付先の自治体から返礼品を受け取ることができます。
注意点
住民税そのものを減らすわけではありません。高額所得者はふるさと納税の枠が大きくなるため、多様な返礼品を受け取る機会が増えます。
仕組み
お住まいの自治体に支払う住民税の一部を、他の自治体に寄付として振り分けます。結果的に、寄付先の自治体から返礼品を受け取ることができます。
注意点
住民税そのものを減らすわけではありません。高額所得者はふるさと納税の枠が大きくなるため、多様な返礼品を受け取る機会が増えます。
医療費控除で思わぬ出費を節税に
医療費控除は、年間10万円を超える医療費が発生した場合、その超過分を所得控除できる制度です。
対象となる費用
・病院の治療費、薬代、手術費用
・家族全員の医療費が対象となるため、家族での合計額がポイントです。
メリット
高額所得者が活用すると、税率が高い分だけ節税効果が大きくなります。
対象となる費用
・病院の治療費、薬代、手術費用
・家族全員の医療費が対象となるため、家族での合計額がポイントです。
メリット
高額所得者が活用すると、税率が高い分だけ節税効果が大きくなります。
住宅ローン控除の活用(条件付き)
住宅ローン控除は、自宅購入時のローン残高の一定割合を所得税から控除できる制度です。
控除の仕組み
・年間のローン残高の0.7%を所得税から控除。
・2000万円以上の収入がある場合、この制度の対象外になる点に注意が必要です。
対象者へのアドバイス
所得制限内であれば、積極的に活用することで大幅な節税が期待できます。
控除の仕組み
・年間のローン残高の0.7%を所得税から控除。
・2000万円以上の収入がある場合、この制度の対象外になる点に注意が必要です。
対象者へのアドバイス
所得制限内であれば、積極的に活用することで大幅な節税が期待できます。
まとめ
給与所得者が利用できる節税対策は、多岐にわたります。iDeCoやNISAなどの投資系制度、ふるさと納税や医療費控除といった仕組みを活用することで、手取り額の向上と将来的な資産形成を両立できます。自身の所得やライフスタイルに合わせて最適な方法を選び、賢く税負担を軽減していきましょう。