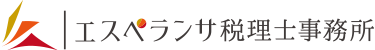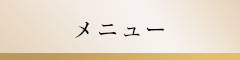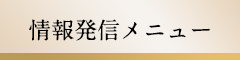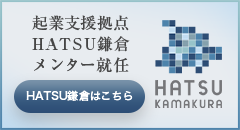給与からの税金や社会保険料の控除が、どのように手取り額に影響しているかご存知でしょうか?
今回は、退職金に関する税金の仕組みについて詳しく解説します。退職金に課される所得税や住民税は、他の所得に比べて大きな優遇措置が設けられています。
ドクターと税金【4】退職金と税金|金融セミナー
目次
- 退職金に課される税金の優遇措置
- 課税額が半分になる仕組み
- 退職所得控除の計算方法
- 退職金を手取りで多く残すためのポイント
- 勤続年数が重要
- 所得税率の影響
- 退職金としての受け取りのメリット
退職金に課される税金の優遇措置
退職金には所得税や住民税が課税されますが、通常の所得よりも優遇された計算方法が適用されます。
退職所得控除後の金額の1/2のみが課税対象となり、残りの1/2は非課税扱いです。この優遇措置により、他の所得に比べて税負担が大幅に軽減されます。
勤続年数に応じて控除額が決まり、退職金から差し引かれます。
20年以下の場合:1年あたり40万円(例:18年勤務の場合、720万円控除)
20年以上の場合:800万円+(70万円 ×(勤続年数 - 20年))
(例:30年勤務の場合、1500万円控除)
これにより、勤続年数が長いほど控除額が増え、手取り額が多くなります。
20年以下の場合:1年あたり40万円(例:18年勤務の場合、720万円控除)
20年以上の場合:800万円+(70万円 ×(勤続年数 - 20年))
(例:30年勤務の場合、1500万円控除)
これにより、勤続年数が長いほど控除額が増え、手取り額が多くなります。
退職金を手取りで多く残すためのポイント
退職金を受け取る際に、手取り額を最大化するためのポイントは以下の通りです。
勤続年数が長いほど退職所得控除額が増えるため、結果的に課税対象金額が減少し、手取り額が多くなります。
控除後の金額に対して適用される所得税率は、累進課税方式(5%~45%)ですが、課税額が1/2になるため、高額所得者でも負担が軽減されます。
通常の給与やボーナスとして受け取るよりも、退職金として受け取る方が税金が優遇されるため、最終的な手取り額が増えます。
退職金は、他の所得に比べて非常に優遇された税金の仕組みが適用されます。退職金の仕組みを正しく理解し、将来の手取り額を計画的に確保していきましょう。
退職金は、他の所得に比べて非常に優遇された税金の仕組みが適用されます。退職金の仕組みを正しく理解し、将来の手取り額を計画的に確保していきましょう。