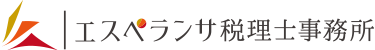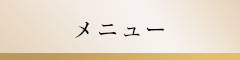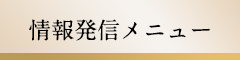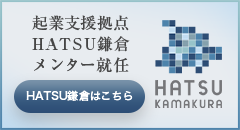給与からの税金や社会保険料の控除が、どのように手取り額に影響しているかご存知でしょうか?
今回は、年末調整と確定申告の違い、確定申告が必要な条件、そして医師の方々が特に注意すべきポイントについて詳しくご紹介します。
ドクターと税金【3】年末調整と確定申告|金融セミナー
目次
- 年末調整で確定申告が不要になる仕組み
- 年末調整とは
- 特例の背景
- 確定申告が必要な条件
- 医師が注意すべきポイント
- 複数勤務による収入
- 配偶者や家族の収入
- 控除の活用
年末調整で確定申告が不要になる仕組み
日本では、給与所得者の多くが年末調整を行うことで確定申告を省略できる仕組みになっています。
毎月の給与から天引きされた所得税の過不足を、12月にまとめて調整する手続きです。不足があれば追加徴収、払いすぎた分は還付されます。この手続きを会社が代行するため、ほとんどの給与所得者は確定申告が不要になります。
全ての人が確定申告を行うのが原則ですが、日本では1億2500万人全員が確定申告を行うと税務署が対応しきれないため、サラリーマンなど給与所得者は年末調整で簡略化されています。
確定申告が必要な条件
医師など高額所得者や副収入のある方は、確定申告が必要となる場合があります。
以下の条件に該当する場合、年末調整だけではなく確定申告が必要です。
✔ 収が2000万円以上
✔ 複数の勤務先から給与を受け取っている場合(例:アルバイトや当直勤務)
✔ 不動産収入や副業収入が年間20万円を超える場合
✔ 医療費控除やふるさと納税を適用する場合
これらの条件に該当する場合、税務署は正確な収入状況を把握する必要があるため、確定申告を義務付けています。
以下の条件に該当する場合、年末調整だけではなく確定申告が必要です。
✔ 収が2000万円以上
✔ 複数の勤務先から給与を受け取っている場合(例:アルバイトや当直勤務)
✔ 不動産収入や副業収入が年間20万円を超える場合
✔ 医療費控除やふるさと納税を適用する場合
これらの条件に該当する場合、税務署は正確な収入状況を把握する必要があるため、確定申告を義務付けています。
医師が注意すべきポイント
医師特有の働き方や収入形態により、確定申告が必要になることが多いです。
医師の場合、勤務先以外のアルバイト収入があるケースが多いため、確定申告が求められることがあります。これには原稿料や講演料なども含まれます。
配偶者や家族が高収入の場合でも、家庭全体で税務管理が必要となるため、確定申告の対象となることがあります。
医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を活用する場合は、確定申告を行う必要があります。これらを正しく申告することで、還付金を受け取れる可能性があります。
年末調整によって多くの給与所得者は確定申告を省略できますが、医師のような高額所得者や複数の収入源がある場合には確定申告が必須となります。
確定申告に関する基本を押さえ、税務手続きの負担軽減に役立ててください。
年末調整によって多くの給与所得者は確定申告を省略できますが、医師のような高額所得者や複数の収入源がある場合には確定申告が必須となります。
確定申告に関する基本を押さえ、税務手続きの負担軽減に役立ててください。