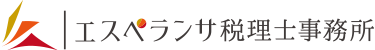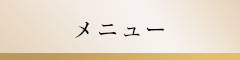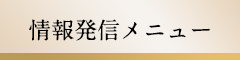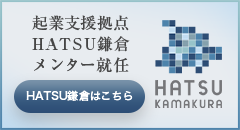給与からの税金や社会保険料の控除が、どのように手取り額に影響しているかご存知でしょうか?
今回は、所得税の計算の仕組みを中心に、年末調整や確定申告の重要性、さらに退職金に関わる税金の優遇措置について詳しくご紹介します。
ドクターと税金【2】所得税の仕組み|金融セミナー
目次
- 所得税の計算方法と控除
- 年末調整と確定申告
- 退職金と税金の優遇措置
所得税の計算方法と控除
所得税は、単純に年収に税率を掛けるだけでなく、いくつかの控除を差し引いた課税所得に対して税率を掛けて計算されます。
給与所得控除
サラリーマンの概算経費として認められる控除。年収850万円を超える場合は控除額が上限195万円に制限されます。
人的控除
基礎控除(48万円)、配偶者控除(38万円)、扶養控除などが含まれます。これらの控除を差し引いた後の金額が課税所得となります。
税率
所得税の税率は累進課税制度を採用しており、5%から最大45%まで7段階に分かれています。高額所得者(年収2800万円以上)は40%以上の税率が適用されます。
給与所得控除
サラリーマンの概算経費として認められる控除。年収850万円を超える場合は控除額が上限195万円に制限されます。
人的控除
基礎控除(48万円)、配偶者控除(38万円)、扶養控除などが含まれます。これらの控除を差し引いた後の金額が課税所得となります。
税率
所得税の税率は累進課税制度を採用しており、5%から最大45%まで7段階に分かれています。高額所得者(年収2800万円以上)は40%以上の税率が適用されます。
年末調整と確定申告
所得税の確定手続きとして、年末調整や確定申告が行われます。
年末調整
サラリーマンが原則として行う手続きで、毎月の給与から天引きされた所得税の過不足を調整します。この仕組みにより、多くの給与所得者は確定申告を省略できます。
確定申告が必要な場合
以下の場合には、年末調整だけではなく確定申告が必要です
・年収2000万円以上
・複数の勤務先から給与を受け取っている
・不動産収入や副業収入が年間20万円以上ある
・医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合
高額所得者や副収入を持つ方は、確定申告が避けられないケースが多いため注意が必要です。
年末調整
サラリーマンが原則として行う手続きで、毎月の給与から天引きされた所得税の過不足を調整します。この仕組みにより、多くの給与所得者は確定申告を省略できます。
確定申告が必要な場合
以下の場合には、年末調整だけではなく確定申告が必要です
・年収2000万円以上
・複数の勤務先から給与を受け取っている
・不動産収入や副業収入が年間20万円以上ある
・医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合
高額所得者や副収入を持つ方は、確定申告が避けられないケースが多いため注意が必要です。
退職金と税金の優遇措置
退職金には所得税や住民税が課税されますが、一般の給与所得に比べて大幅な優遇措置が適用されます。
退職所得控除
20年以下の勤続年数の場合:1年あたり40万円
20年以上の勤続年数の場合:800万円+(70万円 × (勤続年数 - 20年))
例えば、30年間勤務した場合、退職金のうち1500万円分には税金がかかりません。
課税方法
控除後の金額はさらに半分に減額され、その金額に対して所得税率が適用されます。この仕組みにより、退職金の税負担は非常に軽減されています。
高額所得者が多い医師の方々にとって、これらの知識は節税対策やライフプランニングに欠かせません。確定申告が必要な場合や退職時の優遇措置について、しっかりと理解を深めることが重要です。
退職所得控除
20年以下の勤続年数の場合:1年あたり40万円
20年以上の勤続年数の場合:800万円+(70万円 × (勤続年数 - 20年))
例えば、30年間勤務した場合、退職金のうち1500万円分には税金がかかりません。
課税方法
控除後の金額はさらに半分に減額され、その金額に対して所得税率が適用されます。この仕組みにより、退職金の税負担は非常に軽減されています。
高額所得者が多い医師の方々にとって、これらの知識は節税対策やライフプランニングに欠かせません。確定申告が必要な場合や退職時の優遇措置について、しっかりと理解を深めることが重要です。