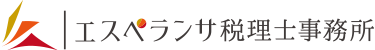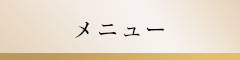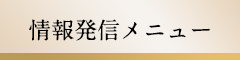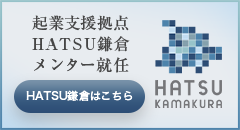給与からの税金や社会保険料の控除が、どのように手取り額に影響しているかご存知でしょうか?
今回は、ドクター向けに、この控除の仕組みとその影響について、さらに医師特有の節税対策と資産運用の基本に焦点を当ててご紹介します。
ドクターと税金【1】給与の仕組み|金融セミナー
目次
- 給与と税金の仕組み
- 社会保険料
- 所得税
- 住民税
- 節税対策と資産運用
給与と税金の仕組み
給与から手取り額が決まるまでには、さまざまな控除が適用されます。給与明細に記載される「総支給額」から、社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険)や所得税、住民税などが差し引かれ、最終的な手取り額が決まります。
健康保険、厚生年金、雇用保険が含まれ、年齢に応じて介護保険も加わります。保険料は4月から6月の給与平均額に基づいて算出されるため、給与の変動に伴い負担額も変わります。
給与総額から社会保険料を引いた金額に基づき、5%から最大45%の税率で計算されます。また、年末調整によって1年の最終的な税額が確定し、不足があれば徴収、払いすぎの場合は還付されます。
前年の収入に基づいて算出され、1年遅れで給与から徴収されるため、所得税と異なる仕組みになっています。会社がまとめて徴収し、個人に代わって自治体へ支払う仕組み(特別徴収)です。
節税対策と資産運用
NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用することで、長期的な資産形成をしつつ税負担を軽減できるのではないでしょうか?
社会保険料や所得税、住民税といった控除がこのように計算されているということをご理解いただければ嬉しく思います。